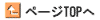HOME > しなびた野菜の復活方法 > しなびたにんじんが元通りになるの?にんじんの復活術、再生術を検証します
|
しなびたにんじんが元通りになるの?にんじんの復活術、再生術を検証します

はじめに
にんじんは水分が多く含まれていて、上手に保存しなければすぐに水分が抜け出てしおれてきます。そこで今回はこうしたしなびたにんじんを再びハリや固さのあるにんじんに復活させる方法を紹介します。さらにその方法が本当に効果があるのかどうかも検証していきます。
しなびる前のにんじん
まずは今回こちらがしなびる前のにんじんです。しっかりとハリと固さがあります。

1本目の重さは186.6gです。

2本目の重さは160.6gです。

こちらを冷蔵庫の野菜室でそのまま保存します。
しなびたにんじん
こちらは冷蔵庫の野菜室でそのまま5日ほど保存したものです。見てわかるほどにしなびています。触るとハリや固さもなく、柔らかくて弾力があります。ところどころ黒いのはにんじんに含まれる色素成分であるポリフェノールの影響で、食べてもとくには問題ないそうです。

ちなみに並べるとこんな感じです。左はしなびる前のにんじんで、右はしなびたにんじんです。だいぶ表面にしわが入っているのがわかるかと思います。

重さをはかってみると1本目は144.9gで当初の186.6gから22.4%減少しています。

2本目は122.0gで当初の160.6gから24.0%減少しています。にんじんに含まれる水分が大きく減少していることがわかります。

しなびたにんじんを再生させる方法その1
コップに水を張り、にんじんのへた側をつけておく
それではしなびたにんじんを再生させる2つの方法を試してみることにします。まずはコップに水を張り、にんじんのへた側の一部分だけ水につけておきます。へたからの水分の吸収を期待するものです。これで一日置いておきます。

このまま冷蔵庫の野菜室に入れ、1日置いておきます。その結果は以下の画像の通りです。
水につけておいたへた側に近い部分はしっかりと水分を吸収してしわもなくなり、ハリや固さも十分あります。

ただ残りの3分の2程はまだしおれていて、触っても柔らかいままです。へたからの水分の吸収がまだ、先のほうまで十分にいきわたっていないようです。
ちなみに並べるとこんな感じです。左はしなびたにんじんで、右はへた側を水に浸けて2日目のしなびたにんじんです。途中までしか戻っていないのがわかるかと思います。

重さは144.9gで当初の186.6gに対して22.4%減だったのが、156.9gで16%減まで戻しています。

3日目の変化
もう1日水にへた側一部だけつけておいてみましたが、以前にんじんの半分以上はしおれたままです。

ちなみに並べるとこんな感じです。左はしなびたにんじんで、真ん中はへた側を水に浸けて2日目のしなびたにんじん、右は再生法3日目のしなびたにんじんです。3日経っても水を浸していない部分は依然としてしなびたままなのがわかるかと思います。

重さは156.3gとなり、何と前日よりも減少してしまいました。

へた側の一部だけをつける方法では、全体に水分をいきわたらせるには限界があるようです。
| 経過日数 | 重さ(増減率) |
|---|---|
| 初日のにんじん | 186.6g |
| 5日目のしなびたにんじん | 144.9g(-22.4%) |
| 水につけて2日目のにんじん | 156.9g(-16%) |
| 水につけて3日目のにんじん | 156.3g(-16.2%) |
へた側をカットして水につける
そこで今度はへた側をカットします。

これを水を吸収しやすくしてさらに1日水につけて置いておくことにします。

1日経過したところ、見た目的にはしなびたままですが、3分の2程は触ると固さが戻ってきています。

やはりカットしたことで給水する力は増したようです。ただ残りの3分の1は相変わらずしなびれていて、柔らかいままでした。
ちなみに並べるとこんな感じです。左上はしなびたにんじんで、右上はへた側を水に浸けて2日目のしなびたにんじん、左下は再生法3日目のにんじん、右下はさらにへた側をカットした再生法4日目のにんじんです。
4日目でも依然として半分以上はしなびたままなのがわかるかと思います。

しなびたにんじんを再生させる方法その2
容器に水を入れにんじん全体を浸す
次に容器に水を入れてにんじん全体がつかるようにします。これでふたをして冷蔵庫の野菜室で保存しておきます。

1日たつと以下の画像のようにしっかりと全体に水分が吸収され、ハリや固さもあり、しわもなくなっています。

ちなみに並べるとこんな感じです。左はしなびたにんじんで、右は全体を水に浸けて2日目のしなびたにんじんです。しっかり全体的にハリが戻っているのがわかるかと思います。

重さも122.2gで当初の160.6gに対して24.0%減だったのが、148.9gで7.3%減にまで戻しています。

1日でしっかりとにんじんを復活させたいなら、へた側の一部だけをつけるのではなくて、全体をつけるようにするといいでしょう。
3日目の変化
さらにもう一日つけておくと、重さは166.3gとなり、今度は逆に元の重さよりも3.5%重くなりました。

触るとしっかりと固くなっています。十分に水分を吸収したことがわかります。

ちなみに並べるとこんな感じです。左はしなびたにんじんで、真ん中は全体を水に浸けて2日目のしなびたにんじん、右は再生法3日目のです。3日目では表面にハリがしっかり戻り、より滑らかになっています。

| 経過日数 | 重さ(増減率) |
|---|---|
| 初日のにんじん | 160.6g |
| 5日目のしなびたにんじん | 122.2g(-24.0%) |
| 水につけて2日目のにんじん | 148.9g(-7.3%) |
| 水につけて3日目のにんじん | 166.3g(+3.5%) |
全体を水に浸けておいたしなびたにんじんと、へた側だけを水に浸けておいたしなびたにんじんを並べてみるとこうなります。全体をつける復活法がいかに効果的なのかがわかるかと思います。

ちなみにしなびたにんじん、しおれたにんじんの再生法については以下の動画でも詳しく解説しているので、併せて参考にしてみてください。
にんじんの保存方法
にんじんは上手に保存しないとすぐに鮮度が落ちてしおれて柔らかくなります。そこで保存法についても紹介します。にんじんは新聞紙に包んでからポリ袋に入れ、冷蔵庫の野菜室で保存します。こうすれば2週間は保存ができます。

他にも茹でたりペースト状にしてから冷凍保存すれば1か月は持ちます。保存方法について詳しくはにんじんの保存方法と保存期間、長持ちのコツで解説しています。

ちなみに以下の動画では実際に新聞紙で包んでポリ袋に入れて保存する方法の効果を検証しています。併せて参考にしてみてください。
にんじんの鮮度を見るポイント
まず購入段階で鮮度のいいものを選ぶのも、にんじんをしおらせてしまわないためには重要です。そこでおいしくて鮮度のいいにんじんを見分けるポイントを紹介します。にんじんは色が鮮やかで表面の凹凸が少なくてなめらかなもの、しっかりと固いものがいいです。
またへたの断面が大きすぎず、黒ずんでいないものも良品です。くわしくはおいしいにんじんの見分け方・選び方でも解説しています。
以下ではにんじんの見分け方・選び方をドアップの映像で動画で解説しているので、併せて参考にしてみてください。
まとめ
今回はしなびたにんじんを再生させる方法についてみていきました。にんじんはそのままだと水分が抜けやすいので、しっかりと保存法を実践して保存しておくことが長持ちの秘訣です。
しなびてしまったにんじんは水につけておくことで、もう一度ハリや固さを取り戻すことができます。水につける場合は、一部だと戻りも一部に限られてしまいます。全体をしっかりと戻したいなら全体を水につけておいた方がいいです。
新版食材図典 生鮮食材篇
野菜のソムリエ