 | 香典の渡し方や金額の相場はいくらぐらい? | |
はじめに
香典はいくらぐらいが相場なの、香典袋(不祝儀袋)にはなんて書けばいいのなどなど、香典に関する疑問は多いかと思います。そこで今回は香典の意味から解説し、香典の形式や書き方、渡し方、香典の相場や香典のお返しの仕方などについて、一から詳しく解説していきます。
香典とは
香典を渡す目的
通夜や告別式で持参する不祝儀を香典と呼びます。香典は故人への弔意(ちょうい・哀悼(あいとう)の気持ち)を表すとともに、遺族に対しては葬儀費用の一部に当ててもらうためのお金です。香典の意義 哀悼の意 葬儀費用の負担
もともとは香のための料金
そもそも香典とは死者の霊に手向ける香のための料金を包んだものです。香典はもともと読み方は同じで「香奠」と表記されていました。奠とは神仏に物を供えて祭るという意味があります。昔は葬儀のための米や麦、香などの現物を弔問客が持ち寄っていたのですが、現在では喪家が香をはじめ葬儀に必要なものを全てそろえます。弔問客は香の代金として現金を持参し、霊前に供えるようになったのです。香典の渡し方
香典を渡すタイミング
香典は通夜・葬式ともに参加する場合は通夜で渡します。受付で簡単にお悔やみの言葉を述べ、相手の前でふくさ又はふろしきから香典を取り出して渡します。 むき出しでは持参しません。通夜で受付がない場合は礼拝のときにご霊前に供えるか、遺族に手渡しします。通夜前の弔問では渡さない
通夜の前に弔問する場合でも香典は持参せず、通夜の際に渡すようにしましょう。これはあらかじめ用意していたということになってしまうからです。お悔やみの言葉は?
お悔やみの言葉は「このたびはご愁傷さまでございます。心からお悔やみ申し上げます。」など。香典の表書き
表書きは宗教によって異なる
香典を包む香典袋(不祝儀袋)の表書きには何と書くかは、宗教によって異なるので注意が必要です。宗教がわからないときは、電話で確認してみてもいいです。ちなみに宗教を問わずに使えるのは「御霊前(ごれいぜん)」です。
仏式は御霊前、御香典
49日の忌明け後の法要までは「御霊前」、それ以後は「御仏前」もしくは「御佛前(ごぶつぜん)」を用いる。 ただし浄土真宗では死後すぐに仏となるという教えから、通夜、葬式の時点で御佛前、御佛前を用います。 仏式で宗派がわからない場合は「御香料」、「御香典」とするのが無難です。ちなみに仏式では蓮の花の絵柄付きの香典袋を使うことがあります。これは仏教では蓮の花は極楽浄土を象徴するものだと考えられているからです。

神式は御玉串料、御榊料
神式の場合は御玉串料(おんたまぐしりょう)がよく使われますが、高額になる場合は御榊料(おさかきりょう)も使います。他にも御神前や御霊前も使えます。御霊前は神式の場合は「みたまえ」と読みます。香典袋(祝儀袋は)柄のついていない無地で白色の物を使います。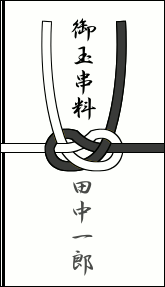
キリスト教式はお花料
キリスト教の場合は葬儀では白い生花の代わりに、お花料として金子を贈ります。金子を入れる不祝儀袋の表書きには、お花料もしくは御花料と記載します。水引には特に決まりはないのでなくてもかまいません。不祝儀袋は白無地もしくは十字架と白いユリが記載されたものを使います。香典袋の表書きについては香典袋の表書きはなんて書くの、御霊前、御佛前、御玉串料、お花料?でも詳しく解説しています。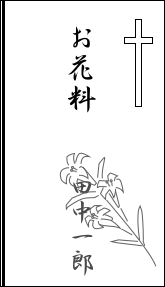
名前は下段中央に
名前は下段の中央に書きます。連名の場合は目上の者を中央に書き、その左に目下の者を書きます。人数が多い場合は代表者を書いてその左に「外一同」と書くか、会社名や部署名を書いてその下に「有志」と付け加え、「〜会社有志」などという風に記載します。そして全員分の氏名を記載した紙を中に入れておきます。この際も右から順に目上の人を記載していきます。
不祝儀袋について
水引の色も宗教で異なる
水引と香典袋(不祝儀袋)などについている紙製の飾りの紐のことです。水引は仏式は白黒、双銀(銀一色)、神式は白黒、双白(白一色)、双銀、キリスト式は水引はつけません。結び方は結び切りで
結び方には、一度結んだらほどけない結び切りと、何度でも結ぶことのできる蝶結びがあります。 蝶結びは何度繰り返しても良い一般的な祝い事に、結び切りは二度と繰り返してはいけない結婚やお悔やみごとなどに使います。 したがって不祝儀袋の結び方は結び切りになります。筆の種類や濃さ
毛筆を使用。「悲しみの涙で文字がにじんでしまった」という意味で、薄墨を使用します。最近では筆ペンで書くことも多いので、普通の濃さでも失礼にはあたりません。包み方
包み方は、お札を裏側にして半紙で包み(中包み)、表側の中央に金額を、裏側に住所と氏名を書きます。香典返しのことも考えて郵便番号、電話番号も忘れずに記載しましょう。次に中包みを奉書紙の真ん中に置き、右・左の潤に折り、上側を下側にかぶせます(上包み)。のし
のしは付けません。のしとは祝儀袋の右側に張る、六角系の形をしたものです。お札
お札は新札だと不幸に対して用意していたという印象を与えてしまうため、失礼とされます。手元にあるお札をそのまま使うといいでしょう。 ただしあまりに汚いお札も失礼ですので、新札でも折り目をつければ良いでしょう。お札を数枚入れる場合は方向をそろえて入れるようにしましょう。数字の書き方
香典袋(不祝儀袋)の中袋の表には金額を記載し、裏には左下に住所と名前を記載します。中袋に記載する数字は漢数字を使います。「金五阡圓」、「金弐萬圓」などの表記が正式なものですが、略式の「金五千円」、「金二万円」という表記でも構いません。
よく使われる数字や漢字は以下のようなものです。括弧表記されているものは正式と略式で表記が異なるもので、カッコ内は略式表記になります。
よく使われる数字や漢字は以下のようなものです。括弧表記されているものは正式と略式で表記が異なるもので、カッコ内は略式表記になります。
| 壱(一)、弐(二)、参(三)、四、五、六、七、八、九、拾(十)、百、阡(千)、萬(万)、阡(千)、圓(円)、金 |
ふくさの包み方
香典袋(不祝儀袋)はそのまま持参するのはマナー違反です。弔事用のふくさか、グレーか紺の地味な色の小さな風呂敷に包んで持参するようにしましょう。正式には弔辞用のふくさは黒色なのですが紫色でも構いません。紫色のふくさであれば弔事、慶事どちらにも使えます。包み方はまずはふくさを斜めに置き、中央右寄りに不祝儀袋を置きます。右の角から折りたたみ、下、上、左の順に折りたたみ、最後に端を裏側に回します。ふくさは必ず使うものなので弔慶用に一枚は用意しておきたいものです。
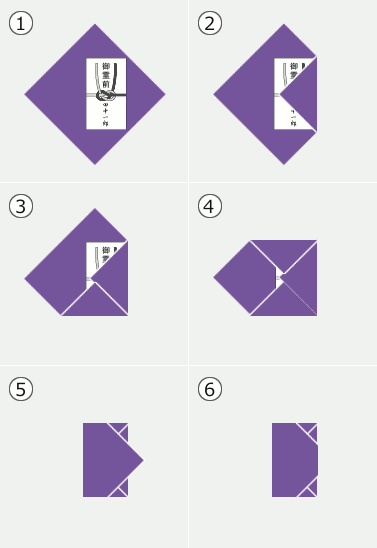
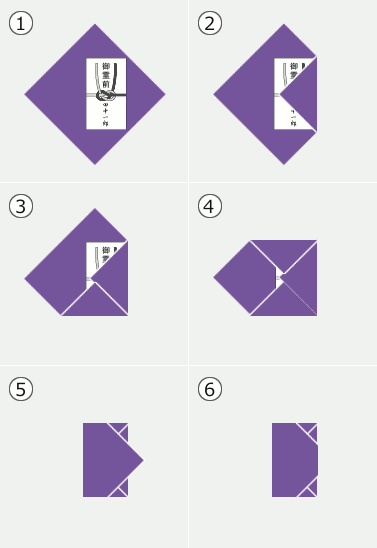
通夜、葬式での香典の相場
香典は故人や遺族との付き合いの程度などで金額を決めます。一般に目上には薄く目下には厚く、身内には葬儀費用の分担の意味も込めて多めに、故人が主人や主婦の場合は多めに、子供や老人の時は少なめでいいとされます。香典は祝儀の場合と比較して送る金額は少なくなります。
香典の金額では、9(苦)や4(死)の数字、偶数は避け、奇数の1、3、5、7、の数字にするのが一般的です。偶数でも2は一般的になってきているので使っても差し支えありません。迷った場合は最初に思いついた額よりも多めにしておくとあとで後悔せずにすみます。
それでは各年代ごとに様々なケースでの香典の金額の目安を一覧表にしてみてみることにします。
香典の金額の目安
香典の金額では、9(苦)や4(死)の数字、偶数は避け、奇数の1、3、5、7、の数字にするのが一般的です。偶数でも2は一般的になってきているので使っても差し支えありません。迷った場合は最初に思いついた額よりも多めにしておくとあとで後悔せずにすみます。
それでは各年代ごとに様々なケースでの香典の金額の目安を一覧表にしてみてみることにします。
香典の金額の目安
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 |
| 祖父母 | 10,000 | 10,000 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 |
| 親 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 兄弟・姉妹 | 30,000〜50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| おじ・おば | 10,000 | 10,000〜20,000 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 |
| おい・めい | 10,000〜30,000 | 10,000〜50,000 | 10,000〜50,000 | 10,000〜50,000 |
| いとこ | 10,000 | 10,000〜20,000 | 10,000〜30,000 | 10,000〜50,000 |
| 友人、知人 | 5,000 | 5,000〜10,000 | 5,000〜10,000 | 5,000〜10,000 |
| 隣近所 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 勤務先の同僚・上司 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 勤務先社員の家族 | 3,000〜5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 取引先関係 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
法要での香典(供物料)の相場
法要での香典(供物料)の相場
法要の際には供物を持参するのが仕来りですが、供物が数多く重なって迷惑な場合もあるため、現在では金子を供物料として持参するのが一般的です。そこで供物料の目安についても紹介します。供物料の金額の目安
| 贈り先 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 |
| 祖父母 | 5,000〜10,000 | 5,000〜30,000 | 5,000〜30,000 | 5,000〜30,000 |
| 親 | 10,000〜50,000 | 30,000〜50,000 | 30,000〜50,000 | 30,000〜50,000 |
| 兄弟・姉妹 | 10,000〜30,000 | 10,000〜30,000 | 10,000〜50,000 | 10,000〜50,000 |
| おじ・おば | 3,000〜10,000 | 5,000〜20,000 | 5,000〜30,000 | 5,000〜30,000 |
| おい・めい | 3,000〜10,000 | 5,000〜20,000 | 5,000〜30,000 | 5,000〜30,000 |
| いとこ | 3,000〜10,000 | 5,000〜10,000 | 5,000〜10,000 | 5,000〜10,000 |
どうしても通夜や葬儀に参加できない場合
どうしても参加できない場合は弔電を打ち、香典を郵送で送ります。弔電(ちょうでん)とはお悔やみのための電報のことです。郵送は香典をいれた不祝儀袋を現金書留封筒にいれて送ります。その際伺えないお詫びの言葉とお悔やみの言葉を書いた手紙を添えましょう。弔電と一緒に電報為替で送金することも出来ますが、受け取り側が郵便局まで行く必要があるため、返って失礼になります。
香典のお返し
仏式は49日又は35日の法要のあと、
神式は50日祭又は、30日祭のあと、
キリスト教式はもともと不祝儀のお返しの制度はないのですが、日本では昇天記念式、追悼ミサの時に送ることが多いです。
表書きでは「志(こころざし)」が宗教を問わず使えます。 この他仏式には「忌明(きめい)」、「忌明志(きめいし)」、「満中陰志」、神式には「偲び草」、「茶の子」などがあります。茶の子は主に関西で使われます。 表書きの裏に贈り人として、葬儀の際の喪主の姓名を書く。
水引きは白黒、双銀。 結び方は結び切り。 金額は半返しで。 実用品を贈る場合が多い。品物は見るたびに故人を思い出さないよう消耗品を送る場合が多いようです。
一家の働き手がなくなった場合などで、養育費に当てるときには、その旨をあいさつ状でおくればお返しは不要です。
表書きでは「志(こころざし)」が宗教を問わず使えます。 この他仏式には「忌明(きめい)」、「忌明志(きめいし)」、「満中陰志」、神式には「偲び草」、「茶の子」などがあります。茶の子は主に関西で使われます。 表書きの裏に贈り人として、葬儀の際の喪主の姓名を書く。
水引きは白黒、双銀。 結び方は結び切り。 金額は半返しで。 実用品を贈る場合が多い。品物は見るたびに故人を思い出さないよう消耗品を送る場合が多いようです。
一家の働き手がなくなった場合などで、養育費に当てるときには、その旨をあいさつ状でおくればお返しは不要です。
香典のお返しが届いたら?
香典(不祝儀)のお返しに対して礼状を送る必要はありません。これは2度とはあってはならない不幸ごとに対して礼を言うのは失礼とされているからです。とはいえ香典返しがしっかりと届いたことは知らせておきたいところです。喪中見舞いもかねたはがきか手紙を送り、その際香典返しが届いたことも記載しておくといいでしょう。「結構なものをいただきまして」、「ありがとうございましたなどの表現は使わないようにします。「届きました」と伝えるだけにしましょう。
親しい間柄なら電話で近況を伺いつつ香典返しが届いたことも知らせるといいでしょう。
親しい間柄なら電話で近況を伺いつつ香典返しが届いたことも知らせるといいでしょう。
香典の即日返し
最近では葬儀の告別式のその日に不祝儀・香典のお返しを渡す「即日返し」も多くなってきています。即日返しの場合は香典が届いたことをあえてこちらから連絡する必要もありません。この場合は香典の金額がわからない状態でお返しをするので送る品は一律2000円〜3000円ぐらいのものを選び、香典で多くの金額をいただいた方には後日改めて別の下の送るようにします。
ご厚志ご辞退の場合は
ご厚志ご辞退とは供物や香典は辞退する、必要ありませんという意味です。遺族や故人、喪主から通夜・葬儀の通知でご厚志ご辞退が記載されている場合は、素直にそれに従うようにしましょう。
まとめ
今回は香典とは何なのか、どのように渡せばいいのか、香典袋の記載の仕方や、香典の金額の相場、香典のお返しの仕方など香典に関しての疑問について解説してきました。宗教によっても香典の様式は異なり、年齢や相手との関係によっても香典の金額は変わってきます。香典を贈る場合は、相手の宗教や相手との関係を踏まえて置くことが重要だといえます。
※ 参考文献
決定版冠婚葬祭マナー事典
すべてがわかる冠婚葬祭マナー大事典
大人のマナー便利帳
社会人のためのマナーとルール
さすが!と言われる図解ビジネスマナー
三越伊勢丹の最新儀式110番
決定版冠婚葬祭マナー事典
すべてがわかる冠婚葬祭マナー大事典
大人のマナー便利帳
社会人のためのマナーとルール
さすが!と言われる図解ビジネスマナー
三越伊勢丹の最新儀式110番
| 最終更新日 2019/08/28 |
 TOPへ TOPへ  マナーTOPへ マナーTOPへ  HOMEへ HOMEへ
|
訪問編一覧
葬式編一覧
その他一覧
PR |
since 2002/09/28
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved
Copyright(C)2002 生活知恵袋 All Rights Reserved



